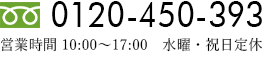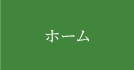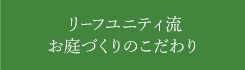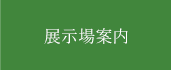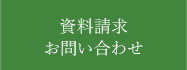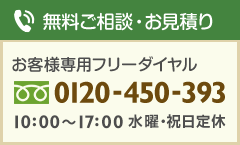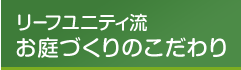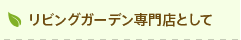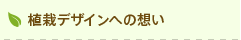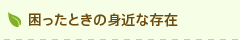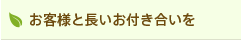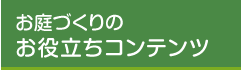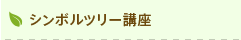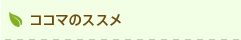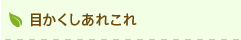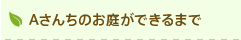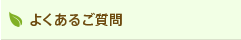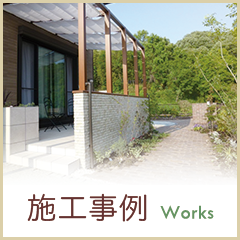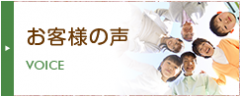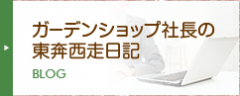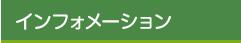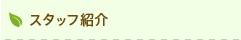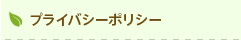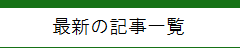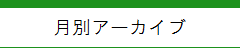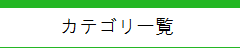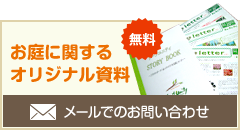その飛鳥の時代の前は、日本書紀では磐余(いわれ)と呼ばれるエリアを転々としていたと記されているわけですが、決して磐余時代とは呼ばれていません。
磐余に考古学的な物証が殆どないため、です。
では何時代、と呼ばれているかと言いますと
「古墳時代」
ですね。
しかし…ですね。
私が小学生の頃は「古墳時代」という時代区分は余り使われていなかったと思うのです。
「大和時代」という時代区分の方がメジャーだった記憶があるのです。
逆に「飛鳥時代」というのは正式な時代区分ではない、と私は理解していたように思います。
それが実際のところどうだったかはともかく
いつしか「大和時代」を「古墳時代」と「飛鳥時代」に分けるように変わっていったんですね。
考古学的な発見と歴史学の研究が進み、そのように変わっていったのでしょう。
特に飛鳥に関しては、現在進行形で様々な発掘調査の成果が上がっているところです。
それも日本書紀の記述との一致が見られているのです。
逆に言うと
考古学的な物証のある飛鳥時代は日本書紀の記述を明確に歴史と認めることができるが
それ以前の日本書紀の記述については明確な歴史として認めていない、という事にもなっています。
もちろん神話の時代から始まる日本書紀の記述の前半は殆どが創作でしょう。
しかし飛鳥の時代は史実。
それならば飛鳥の直前の磐余の時代もそれなりに史実を反映しているのだろう、と考えることもできます。
しかし学校の歴史、という分野においては飛鳥時代の前の時代については
明らかに考古学的にも残されている古墳、というものを根拠としたものでしかありません。
前方後円墳が全国的に分布し、特に大型のものが奈良や大阪に集中している。
と、いう事は奈良や大阪を基盤とした全国的な王権が存在した事を示している。
しかし古墳を発掘しても、殆ど文字というものがありません。
出てくるのは埴輪や各種の道具ばかり。
そして一部の中国の歴史書に、僅かに当時の日本の記録がある。
それらの情報を学校の教科書の歴史として認定しているに過ぎない時代なんですね。
なので都がどこにあったとか
日本書紀には登場する天皇等についても教科書には殆ど書かれていないわけです。
あくまで全国的に古墳が作られた時代、というレベルに留めて「古墳時代」と区分しているんですね。
一方で何度も書いていますが、飛鳥の時代については明確な、そして多岐に渡る発掘調査の成果が出ているんです。
もう一つ言うと有名な聖徳太子が送った遣隋使。
日本書紀に記述があるとともに、隋という中国の国の歴史書にも記述がある。
これはもう、史実でしょうという事になるわけです。
よって「飛鳥時代」から、教科書にも固有名詞がバンバン登場すて歴史が動いていくのです。