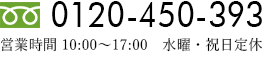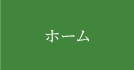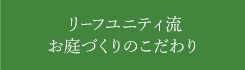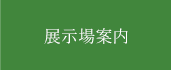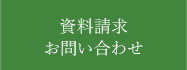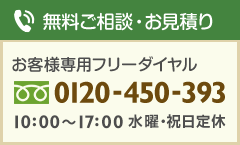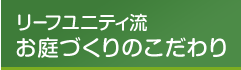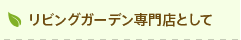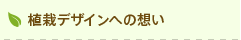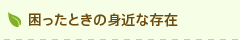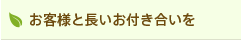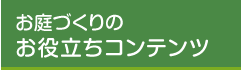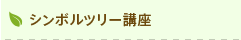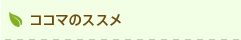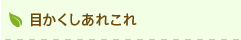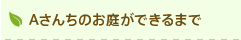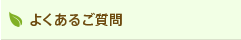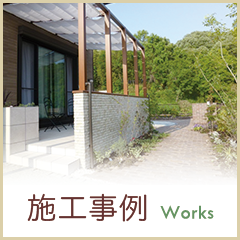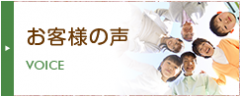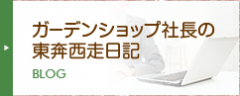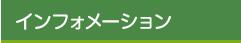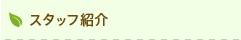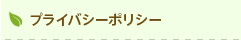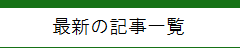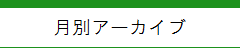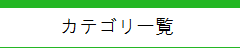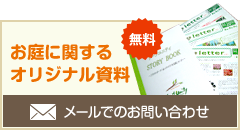起床は4時台です。
4時10分のときもあれば4時50分のときもありますが、目覚ましなしで起きられるので4時台に目覚めたら二度寝(というか実際は三度寝、四度寝)せずに起きてしまいます。
朝起きたら自宅にて
読書(1~2分程度)
ジャーナリング(日誌を書く) 読書から得たことを書き留めるところから
その後風呂に入り、湯船で深呼吸10回
出勤後に
ゴミを何か一つ捨てる
ハガキ一枚、メール一通
その後、腕立て伏せとスクワット
後の時間で経営について考える
その後、土場に移動して朝礼は7時30分からスタート。
日々これらを当たり前にこなしているので、もはや自動的にやっている感じです。
そして、その中でも3年くらい続いている腕立て伏せなのですが
さすがに筋肉が付いてきていることを実感しています。
いやま、本格的な筋トレしている人からすれば全然大したことないんでしょうけど^^;
でもね…
実は私、人生において筋トレとかしたことなかったんですよ。
筋トレに限らず、スポーツとは全く無縁の文科系人間でした^^;
なので、どうも慣れない筋肉っていうやつに違和感も感じつつも、やはりちょっと嬉しいものです(^^)/
腕立て伏せなんで、ほぼ腕だけなんですけどね^^;
スクワットによる足の筋肉は未だ体感に至っておりません…。
ともあれルーティーンというヤツは重要だと感じます。
そして、やはりルーティーンは朝が大事です。
最初はスクワットを夜にやろうとしたんですが、様々な理由でできない日ができてしまうんですね。その点、朝は何にも邪魔されないので間違いなくこなせていけるんです。
継続は力なり、とよく言われますが
継続、すなわちルーティーンです。
習慣、という言葉にもなりますが日本語の習慣と書くとちょっとフワッとした印象になります。
そういうわけで
また新たなルーティーンを作れないかな…と考える毎日です。