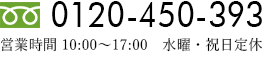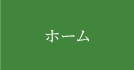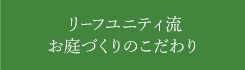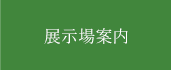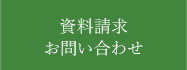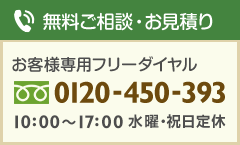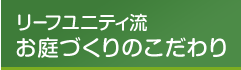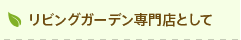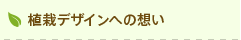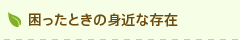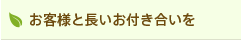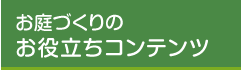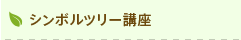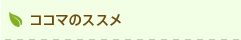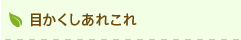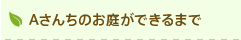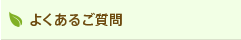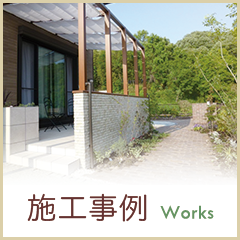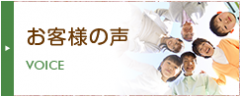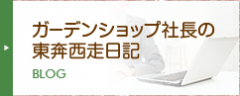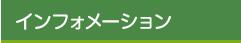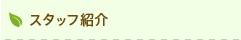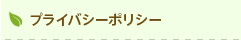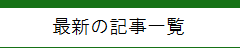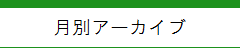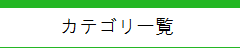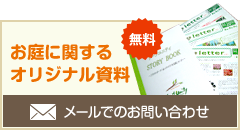ガーデンショップ社長の東奔西走日記

先日、高校2年生のインターンシップを受け入れたのですが
来てくれていた生徒さんたち3人から「お礼状」が届きました!
読んでみると
「拝啓」から始まる手紙の定型があり、締めくくりから全体のレイアウトもほとんど同じですが
一文だけ、自分の言葉で書いたかのような文章がありました。
クラスみんなでワイワイと、手紙の書き方を先生に教えてもらいながら書いたんだろうな~、なんて想像しながら読ませてもらいました。
直筆の手紙って、やっぱり何か嬉しいものですね(^^)
もちろん、これは学校としてインターンシップ受け入れ企業へお礼状を送るという「型」があるから送られてきたものです。生徒個人が考えたわけではない行動です。
それでも、受け取った人間は素直に嬉しく感じる。
そう思うと、やはり「型」って大事ですね~。
ここはやはり、ビジネスの世界の人間として学ばねばなりません。
今日のお礼状は封筒に入った手紙でしたが、ハガキなら更に郵送コストも安い。
僅か52円のハガキに凄いパフォーマンスがある、という話は時折聞くものです。
また、社内の話になりますが
サンクスカード
なるものもありますね。
こういったものも「型」、言い換えれば「ルール」がなければ誰も書きません。
「ルールがあるから書いた」ものであっても、もらった方は嬉しい気持ちになる。
御礼を紙に書く。
大事なことですね…!
ちょっと改めて考えさせてもらいました!
改めて言うのも何なのですけど
当社には大きな強みがあります。
それは、展示場です。
田舎ならでは(!?)のメリットを生かした広さ自慢、そして園芸店とカフェ併設の展示場。
私としては、引き継いだ者なのでエラそうには言えませんし
正直、自分でやれと言われてもとてもできない規模の展示場を保有しているのです。
しかし
では、その展示場を生かした営業・マーケティングがどれだけできているのか…?
実は
さほどでもないんですね…
展示場整備については、もちろん継続的にコストをかけてやってきました。
しかし、あまりにも広いという事もあって一気に作りこむことは不可能でした。
また、展示場といっても
展示すれば売れるというものでも何でもありません。
そもそも、気を抜けばあっと言う間に雑草畑になってしまうという環境です。
雑草対策をするための「型」を作るだけでも、長い年数がかかってきたのです。
少しづつ、無理のない範囲で整備・投資を続けてきました。
30周年にあたってショールームをリニューアルしました。
自社の成長ステージと取り巻く環境も少しづつ変化してきています。
そして、これから。
目指す目標のためにも、新たな舵を切ります。
大きなテーマは
植栽。
植栽の魅力を伝える展示場をつくります。
いつも花いっぱいの展示場をつくります。
地域の方々が気軽に立ち寄りたくなる展示場をつくります。
そして
植栽デザインで更なるステージアップを目指していきます。
2016年は、そんな新たな一歩を踏み出す年にしたいと思います。
これが採用サイトだ!
↓
さて、ブログの方も加速していきたいと思います。
と、言うのも
なんと3000本投稿に迫ってきているのです~!
書き始めたのが、実に11年前。
しかも、ライブドア一筋。
別にライブドアに思い入れも何もありませんが、ただただ継続してきただけです。
しかし実は
とうとうライブドアを卒業することになりました(何を大層な!?)。
これには深~い理由があるのですけど
それは今は書くのを控えておきます。
これから卒業準備に入るので、実際は6月ごろに新しいブログに移る予定です。
この投稿が2976本目となっており、順調に行けば2月には3000本達成となるわけで
3000本を達成してライブドア卒業という素晴らしいタイミングとなる予定です。
3000本、どうです~!?
野球で言うなら張本ですよ!?(笑)。
これも、11年の継続の結果です。
1年に300本書いて10年かかるんですよ!?
念のため言いますが、内容の薄い短いブログとかは基本書いてませんから。
飲み会やら今日のランチ、とか絶対に書いてませんから(笑)。
過去のブログで阪神ネタを長々と語ったりしていますが、あくまで真剣で深い内容ですから(笑)。
ともあれ
当社の経営理念であり、私自身の座右の銘とも言える
「継続が幸福を導く」
の象徴と言えるかも知れません。
そしてこれからも
書き続けるんです!
これが採用サイトだ!
↓
フェイスブックで誰かが「いいね」した記事のリンク先で、こんなような事が書いてありました。
「自分の願望などを、常に回りの人間に発信し続けていると情報が入ってきたり協力者が現れたりして実際に上手くいく方向に流れる」
みたいなカンジの話でした。
ふーむ、なるほど。
そういうわけで、ブログにも書くことにしましょう。
これ、同業他社さんに知られるというデメリットもあるのですがメリットの方が多いと信じて公表しちゃいます。まあ別に私の会社ごときの話、知られても影響などないですかね(笑)。
実は私にはビジネス上の野望が一つありまして…
それは、大阪進出です。
ビジネス戦略までは書きませんが、実は色々な理由、狙いがあります。
先日早速あるところで、ある方にこの話をさせていただきましたところ…
「それなら、早速協力できるよ」
と、予想以上にダイレクトな反応をいただきました。
その方と別れて2時間後くらいに
「さっそく話しといたから」
あっという間に、ある大阪の方との橋渡しをしてくださったのです。
すごいな、これ。
言ってみるものやな、と思いました。
しばらく、この話してまわろう(笑)
そういう訳で
大阪行きます。
大阪府下の現場は、これまでからずっと手掛けてきたのですが
さらに積極的に取り組んで行きます。
拠点を出すのは先の話ですが
現場は、すぐにでも行けますから。
過去に縁あって大阪方面に行く機会が増えた時期もありました。
当時「和泉市ってどこですか?」なんて始めは言ってたのですが、その後現場も増えて実はそれなりに土地勘もできたのです。当時、思えばナビなしでよく行ってたな(笑)今はタブレットのナビがあるから安心です
大阪で外構エクステリア業者をお求めの住宅関連業者の方々
奈良からひと山越えてヒョイッとまいります。
住宅外構専門です。
植栽は特に得意です。
奈良のリーフユニティにお任せくださいませ…!
これが採用サイトだ!
↓
さて
仕事始めから4日目。
あっという間に日常フル回転状態に突入しています(・・;)
しかし、せっかくの新年ですから心機一転です!
まずは新しい「経営指針書」をスタッフに配布しての年頭訓示。
これまでの「経営方針書」からグッとステップアップして、中期ヴィジョン、単年度計画などを語りました。
そして、そこにも記載した今年のスローガンは
「凡事徹底」
です。
この言葉は、イエローハットの創業者である鍵山秀三郎氏によって強く語られていることで有名です。
以下、コピペです。
私がいままで歩いてきた人生をひと言で表現すると、「凡事徹底」。
つまり「誰にでもできる平凡なことを、誰にもできないくらい徹底して続けてきた」ということに尽きます。
人が見過ごしたり、見逃したり、見捨てたりしたものをひとつひとつ拾い上げ、価値を見出す。
やれば誰でもできる平凡なことを徹底して、そのなかで差をつける。
そんな信念を持って、いままで生きてきました。
ともすると人間は、平凡なことはバカにしたり、軽くあしらいがちです。
難しくて特別なことをしなければ、成果が上がらないように思い込んでいる人が多くいます。
そんなことは決してありません。
世の中のことは、平凡の積み重ねが非凡を招くようになっています。
いつも難しくて大きなことばかりを考える人は、失敗したり続かなかったりして元へ戻ってしまうことが多いものです。
できそうにない特別なことばかり追いかけるよりも、誰にでもできる平凡なことを少しずつでも積み重ねていけば、とてつもなく大きな力になることを知るべきです。
平凡なことを徹底して続ければ、平凡のなかから生まれてくる非凡が、いつかは人を感動させると確信しています。
***
この言葉、当社の経営理念「継続が幸福を導く」にも当てはまる、素晴らしい言葉だと思います。
スローガンって、強い縛りのあるルールでも何でもないです。
しかし、この短い言葉(当社では例年四字熟語のスローガン)が普段の行動を何気なく後押ししてくれる時があるんですね。
ちなみに過去のスローガンは
全員一丸
日々成長
環境整備
事前準備
改善実行
そして今年が
凡事徹底
です!
今年も良いスローガンができました…!
これが採用サイトだ!
↓
皆様
新年あけましておめでとうございます。
本年も変わらぬご愛顧を賜わりますようお願いいたします。
2016年、いよいよ待ったなしで取り組みべきことが山積みの年となります。
昨年既に社内の業務体制の変革にハンドルを切りました。
これは絶対に推し進めていかねばならない大きなテーマです。
そして今年は年頭訓示に、新たな「経営指針書」を配布すべく準備をしてきました。
6日の年頭訓示で配布いたします。
ここから3年後、そして5年後を見据えて動き出します。
昨年、様々な出会いや学びがあるなかで、ハッキリと自分の中で将来へのヴィジョンが湧き起ってきたのです。
正月早々、モチベーションはマックスです。
ところで、このブログを書くにあたって昨年の年頭ブログを読み返したのですけど
重大なテーマが未達となってしまいました…(・・;)
と、いうのも
ダイエット。
ダイエット年間にする、とか書いてましたね…。
真逆に結果になってしまいました…(泣)
もう誰も信じてくれないかも知れませんが
一応、ダイエットのやり方は心得ているつもりでして
懲りずに宣言いたします、ハイ…。
目標 -5㎏ in 5月
いや、今年はやりますって(笑)。
これが採用サイトだ!
↓
本日が仕事納めの日。
最後の夕礼も終え、スタッフもみんな上がってくれました。
1年間、お疲れ様でした。
ここで1年間を振り返るのも、当ブログの恒例です。
昨年から今年の6月までを30周年の期間と位置づけ、昨年を漢字一字であらわすと「周」といたしました(世間では「税」でした)。
今年は「新」といたしましょう(世間では安保法案のイメージが強かったのか「安」でした)。
今年は30周年を終え、新たな視点で臨む年となりました。
大阪進出計画、そしてその先にある大きな目標。これらを30周年の打ち上げパーティで社員さんに発表しました。
4月に迎えた新卒の新入社員。新卒採用ははじめての取り組みだったのですが、二人の将来有望な若い子が仲間として加わってくれたのです。
二人が入ってくれたことによって吹き込んだ新しい風。
何か、新しい大きな一歩を前進できたように思います。
そんな2015年。
「改善実行」をスローガンとして掲げ、あらゆる業務の改善を目指した。
30周年記念事業として展示場整備とともに記念植樹を行った。
30周年打ち上げパーティを行い、永年勤続者を表彰した。
高卒の新入社員二人を迎え、彼らの成長に周りの人間も新鮮な気持ちになれた。
スタッフは一人産休に入ったが、逆に産休に入っていたスタッフが3人復帰してくれて充実した体制になった。
カフェの植栽を手がけさせていただき、個人的にも思い出の現場になった。
桜井駅前で古墳の形の広場の工事を手がけさせてもらった。
その他、大型の現場の御縁を多くちょうだいした。
各方面のお得意先様から大きな期待をいただき、シェアを伸ばすことができた。
内勤朝礼、メール配信、内勤日報、経営方針書読み合わせなど新たな取り組みの「型」を作った。
設計積算部を稼働し、社内システムの構築に大きな一歩を踏み出した。
そして植田の個人としては、中小企業家同友会との関わりがありました。
もしかして終生目指していくかもしれない存在との出会いがあり、そして経営者を前にした経営体験報告をさせてもらった。
埼玉、広島、島根、山梨へ行って全国の青年経営者と出会い、そして関わり、多くのことを学ぶことができた。
会社としても、そして個人としても
色んな意味で、過去にない新しい1年になったのではないかと思います。
今年もいただいた、各方面様々な方々とのご縁。
この場を借りて、改めて厚く御礼申し上げます。
迎える2016年。
本当に待ったなしで会社が大きく変わる年になります。
素晴らしいチャンスの1年にしたいと思います。
また来年
皆様どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
よいお年を…!
クリスマスイブも、何もあったものじゃありません。
怒涛の12月、散髪に行く日がどうしても取れず、やむを得ずこれから散髪に行く植田です^^;
忘年会等は先週に概ね終わり、今週は予定を入れないでおいてよかったです。。
当社は29日まで営業となります。
業界的には28日までのところも多いのですけど、「年内完工」の予備的な意味合いも込めて29日までとしています。
一部の担当者が29日まで頑張って他の者が休んでいる、という図式を避けたいという思いが込められて毎年この日程としています。
今年も、どうやら29日までフル回転の見通しです…。
何が何でも、やり切ります!